しば漬、千枚漬とともに京都の三大漬物といわれる「すぐき」。冬の食卓の名脇役として、また贈答品の定番として長く親しまれてきました。 今回は京都市北区上賀茂で「すぐき」の伝承に尽力されてきた戸田秀司さんのお話をもとに、「すぐき」の背景にある知られざるストーリーをご紹介します。
上賀茂地域の伝統産品
鼻に抜けるさわやかな香りと、発酵食品ならではの角のない優しい酸味。そこにシャキッとした歯触りがあいまってついつい箸が伸びてしまう「すぐき」は、数ある京都の伝統料理の中でも独特の存在感を放っています。

そもそも、「すぐき」は京都の人でなければ聞き馴染みがないかもしれません。原材料である「すぐき菜(すぐきかぶら)」は縦長の蕪の一種で、京都市北区上賀茂地域で伝統的に栽培されてきた野菜。毎年11月から12月にかけて収穫し、そのほとんどが漬物用として使われるといいます。塩で漬け込んで乳酸発酵させることで独特の酸味が生まれることから、「酸茎(すぐき)」と名付けられたと考えられています。
葉は適度な長さに刻んで、かぶらはある程度厚みをもたせて食べるのが一般的。酸味がお米の甘味を引き立ててくれるので、ご飯のお供やお茶漬けにして食べられることが多く、お酒との相性も抜群。細かく刻んでチャーハンの具にしたり、ピクルスのかわりにサンドイッチに使ってみるのもおすすめです。


味の良さだけでなく、近年では「すぐき」に「ラブレ菌」が含まれていることがわかり、健康食材としても注目されるように。「ラブレ菌」は、腸の中で良い働きをするとされている乳酸菌の一種で、免疫力の向上をはじめとする健康効果が期待されています。
使い勝手が良く、身体にも良い。さらに収穫から間もないフレッシュな新漬けと、発酵が進んで味が馴れてくる春・夏の味を食べ比べてみるのもおすすめ。「すぐき」は食卓の万能選手でもあるのです。
シンプルでも、手間ひまをかけて
「すぐき」は原材料であるすぐき菜と、塩のみでつくるシンプルな漬物です。もともとは上賀茂の限られた地域の生産者が栽培から加工、販売までを手掛けてきたため、それぞれの家(生産者)ごとに製法や味が異なりますが、工程は大きく「荒漬け」「本漬け」「室入れ」に分かれます。

表面の皮やひげを包丁で落としたすぐき菜を樽に入れ、大量の塩を振って一晩漬け込む「荒漬け」を終えると、樽の底からすぐき菜を渦巻き状に敷き詰め、一段ずつ塩を振る「本漬け」に。生産者によっては、圧力をかけるために丸太棒と重石を使う「天秤押し」という伝統技法を、今でも使用しています。
強い圧力をかけながらじっくりと漬け込んだ後は、約40℃の室温を保った「室」で一週間ほど寝かせます。この工程で乳酸発酵が促され、爽やかな酸味がもたらされます。


献上品から全国区の漬物へ
すぐき菜の確かな歴史を記した目立った文献は見つかっておらず、口伝によればその発祥は安土桃山時代といわれ、賀茂別雷神社(上賀茂神社)の社家(代々神社の奉祀を行ってきた身分・氏族)が賀茂の河原で偶然発見した、あるいは天皇家から賜った珍しいカブを栽培したことがはじまりであるとする2つの説があります。


「当初は、御所との所縁が深い上賀茂神社の社家によって栽培され、宮中に献上されてきたと思われますが、江戸時代末期に神社周辺の4軒の農家だけに種が配られ、栽培が許されたと聞いています」と戸田さん。
徐々に上賀茂一帯に生産が広がり、皇室が東京に移った明治維新以降は「振り売り」によって京都の旦那衆の口に入るように。その後は大阪商人を通して全国に贈られるようになりました。
「私の祖母も大阪で振り売りをしていて、「すぐき」はよく売れたそうです。やがて大阪や京都の漬物屋が扱い出し、大阪中央市場に「すぐき」のせり市ができ、お歳暮向けの贈答品としても定着していきました」(戸田さん)。

「すぐき倶楽部」発足の背景にあった危機感
上賀茂神社の社家による門外不出の品から、全国的な知名度をもつに至った「すぐき」。拡大するニーズに応えるべく、生産者は最大で約200軒にまで拡大したといいます。
バブル景気が追い風になったこともあり、「すぐき」は上賀茂の農業全体をも活気付けましたが、バブル崩壊後は徐々に売れ残りが目立つように。コスト削減を図る生産者が生産工程を無理に短縮したことで味が落ち、さらに売れなくなるという悪循環も生じていました。
「あるお客様から『「すぐき」は買うものではなく貰うもの、そしてほかす(捨てる)もんや』といわれたときは、ショックで返す言葉もありませんでした」と、過去の悔しい経験を振り返る戸田さん。地域の伝統の灯を絶やすまいと奮闘する中で、仲間とともに立ち上げたのが「すぐき俱楽部」(当時は「特産研究会」)です。
生産者ごとに製法や味が異なる点は「すぐき」の魅力の一つですが、その違いがあまりに大きければ「すぐき」全体の評判を落としかねません。玉石混交の状態を改善すべく、倶楽部のメンバーがまず取り組んだのは、勉強会を開き、互いの製造現場を見学し合うことでした。本来、各家に伝わってきた製法は門外不出であり、他家に明かすことはご法度とされていたことを思えば、メンバーが当時抱えていた危機感や覚悟の程が察せられます。
「家ごとに違う味を統一するのか、という意見もありましたが、私たちがやりたかったのは統一ではなく、あくまでメンバーのレベルアップです」と語る戸田さん。4年間継続して取り組んだことで、目に見えて品質が底上げされていきました。

他にも京都駅でアンケート調査を行って知名度を調べたり、テレビや新聞をはじめとするメディアへの露出と広告出稿を積極的に行ってきたすぐき倶楽部。この時代の精力的な活動がなければ、「すぐき」という伝統食品が今も私たちの食卓に上る機会は、なかったかもしれないのです。
「自分だけではなく、地元の協力者がいてくれたからこそできたこと」と仲間への感謝を口にする戸田さん。「すぐき」を守るべく取り組んできたマーケティングやブランディングの手法は、同じく上賀茂特産の「賀茂なす」の成功にも大きな影響を及ぼしています。
進むべき道
「すぐき俱楽部」には現在も約30名の生産者が名を連ね、ときには情報を交換し、ときには切磋琢磨しながら、「すぐき」の価値を守り続けています。
上賀茂神社の協力を得て、毎年12月初旬に開催する「すぐき道中」も、すっかり季節の恒例行事として定着。当日はメディアが取材に訪れ、参拝者に新すぐきの無料配布を行うなど、貴重なPRの場になっています。



「全盛期に比べると数こそ減っていますが、現役世代の取り組みぶりは頼もしく感じています」と目を細める戸田さん。後進の進むべき道を作った現在も、「すぐき」の無形文化財登録を目指して忙しい日々を送っています。
「京漬物はたくさんあれど、「すぐき」ほどぜいたくな漬物はないと思っています。冬の寒い時期に全て手仕事で、時には重たい石を抱えたり、何度も何度も塩を振ったり。先人から受け継いだ製法を守りながら、手間を惜しまず現在まで作り続けてきた上賀茂伝統の味ですから、もっと多くの人に食べていただけるよう、皆で盛り上げていきたいと思います」。
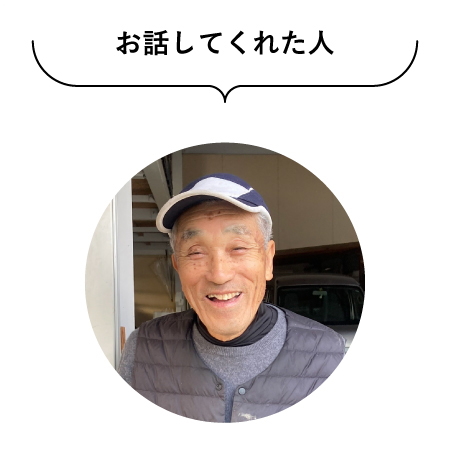
戸田秀司さん
JA京都市 上賀茂支部
上賀茂地域で賀茂なすや「すぐき」を中心に25品目を栽培。
上賀茂特産野菜研究会や洛北農業クラブの創設など地域農業の活性化に尽力。2015年から京都市農業協同組合代表理事組合長に就任。2024年に組合長退任すると、上賀茂支部の組合員としてすぐき栽培などに取り組む。
●動画 京都上賀茂特産「すぐき」ができるまで
●「すぐき」を使ったアレンジレシピはこちら
